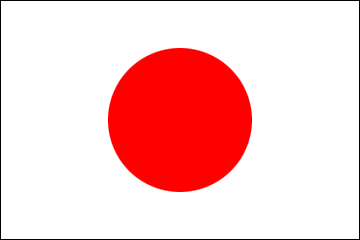領事関連情報
国籍について
1.日本国籍の取得
日本の国籍を取得するのは、次の3つの場合です。
1. 出生によって日本国籍を取得する場合
- 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
- 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
上記にある「父」とあるのは、生物学的なものではなく、あくまでも、その生みの母と法律上の婚姻(民法739条)している者でなければなりません。そして、法律上有効な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子を法律上「嫡出子」といいます。民法は、父母の婚姻を基準として、「嫡出子」と「嫡出でない子」とを区別しています。
すなわち、子が嫡出子であれば、上記a.にあるとおり、その子は当然に日本国籍を取得します。もっとも、子の出生時に父母が婚姻していなくても、母とその子(いまだ嫡出でない子)との親子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生するとするのが通説です(最高裁判例)。
従って、日本人女性が外国人男性と婚姻をしないで、その間に生まれた子(嫡出でない子)は、子の出生の時に、法律上の父子関係が成立していませんが、分娩の事実により法律上の母子関係が発生していますので、子は出生により日本国籍を取得します。
それに対して、日本人男性が外国人女性と婚姻をしないで、その間に生まれた子(嫡出でない子)は、子の出生の時に法律上の父子関係が成立していませんので、日本国籍を取得することはできません。もっとも、日本人男性が胎児認知(民法783条)している場合は、その子は、父からみて、未だ嫡出でない子ですが、法的な親子関係を発生させる認知の効果から、例外として、子は出生により日本国籍を取得することができます。
なお、「出生の届出」については、「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない。」と定められています(戸籍法49条)。一方、国籍法第12条には、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」と規定されています。
従って、たとえば、「日本国籍」と「タイ国籍」とを持つ子がタイ国で産まれた場合に、出生の時から「3ヶ月以内」に日本国籍を留保する意思を表示した出生届を出さないと、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。本条はこのように国籍の得喪を左右する大変重要な規定であるといえます。
人は、出生によって権利能力を取得し、あらゆる法律行為の主体となります。また、出生の事実は、人が国籍を原始的に取得する原因となります。出生届は、人としての始期を登録公証するものであり、この出生届をすることによって、これらの事実が明らかにされます。出生の届出はこのように重要な届出であります。
2. 法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する場合
国籍法第3条の「認知」による国籍の取得の場合
上述したように、日本人父と外国人母との間で、その婚姻前に生まれた子は、その出生の時に、父と法律上の父子関係がありませんので、出生によって日本国籍を取得することはできません。
国籍法第3条はこのような子の日本国籍の取得について次のように定めています。すなわち、出生後に父又は母が認知した子で、18歳未満の者(日本国民であった者は除外します。)は、認知した父又は母が、その子が生まれた時に日本国民であって、しかも、現在も(死亡していれば死亡のときに)日本国民であるとき(あったとき)は、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。 この届出は国籍取得届といい、その届出のときに子は日本国籍を取得します。
【認知による国籍取得届必要書類】
- 国籍取得届(当館にあり) 2通
- 写真(縦横4.5cm、親子3人の上半身写真) 2枚
- 認知に至った経緯等を記載した父母からの申述書 父母各1通
*外国文の場合は日本語訳の添付が必要。
*添付できないときはその理由を記載した書面の提出が必要。
「認知に至った経緯等を記載した申述書」の書式 父用
 母用
母用 

- 国籍を取得しようとする者を母が懐胎した時期に係わる父母の渡航履歴を証明する書類(パスポート等) 1通
*外国文の場合は日本語訳の添付が必要。
*添付できないときはその理由を記載した書面の提出が必要。なお、認知の裁判が確定している場合は提出しなくてもよい。 - 国籍の取得をしようとする者のタイ国住居登録証(原本に限る) 1通
- 上記和訳文(要 翻訳者名明記) 1通
「タイ国住居登録証」の和訳書式

- 国籍の取得をしようとする者のタイ国出生登録証(原本に限る) 1通
*国籍の取得をしようとする者が日本国内で出生した場合は、出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書の提出が必要。 - 上記和訳文(要 翻訳者名明記) 1通
「出生登録証」の和訳書式

「出生登録証」の和訳書式記入見本

【備考】
- 関係者(父・母・子)は手続き時に当館にお越しください。
- 国籍の取得をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人(通常は父母)が届出人となります。
- 国籍の取得をしようとする者が居住する場所を管轄する法務局又は地方法務局及び在外公館でのみ提出可能です。
- 国籍取得届提出後、およそ3ヶ月で、法務省より提出先公館等に国籍取得証明書が郵送されます。その後、当該証明書に基づき国籍を取得した者の戸籍への入籍手続きを行います。入籍手続きが完了して初めて日本国旅券の申請が可能となります。
国籍法第17条第1項の国籍の再取得の場合
上述したように、外国で生まれ、出生によって日本国籍のほかに外国の国籍をも取得した子は、出生の時から「3ヶ月以内」に日本国籍を留保する意思を表示した出生届を出さないと、その子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます(国籍法12条、戸籍法49条)。
本規定により、日本国籍を失った18歳未満の人は、日本に住所がある場合、国籍の再取得の届出をすることができます(国籍法17条1項)。
一方、重国籍者で、官報によって法務大臣から国籍選択の催告(「国籍の選択制度」の箇所で詳述)を受けたのに、1ヶ月以内に日本の国籍を選択しなかった人は日本の国籍を失ってしまいます。このような人は国籍法第5条第5項(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)を備えるときは、日本の国籍を失ったことを知った時から1年以内に、国籍の再取得の届出をすることができます(国籍法17条2項)。
なお、国籍の再取得の届出の詳細については、日本の法務局又は地方法務局  にご相談ください。
にご相談ください。
3. 帰化によって日本国籍を取得する場合
外国人が日本に帰化するには法務大臣の許可が必要で、住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止等が定められています。詳細については、日本の法務局又は地方法務局にご相談ください。
2.国籍の選択制度
我が国の国籍法は重国籍の人に対して、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択するように義務づけています。
国籍選択制度の概略は以下のとおりです。
1. 国籍の選択をしなければならない人
重国籍になる例としては、次のような場合があります。
- 日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子。
- 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子。
- 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国で生まれた子。
- 外国人父からの認知、外国人との養子縁組あるいは外国人との婚姻などの身分行為によって外国の国籍を取得した日本国民。
- 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人。
2. 国籍選択の方法
国籍を選択するには、自己の意思に基づき、次のいずれかの方法により選択して下さい。
日本国籍を選択する場合
(イ)外国の国籍を離脱する方法。
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して大使館領事部または市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。
(ロ)日本国籍選択の宣言をする方法
重国籍者で日本国籍を選択する人は、大使館領事部または市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」をして下さい(タイ国籍との重国籍者で日本の国籍を選択する人はこの方法によることになります)。
外国の国籍を選択する場合
(イ)日本の国籍を離脱する方法。
重国籍者で、外国国籍を選択する人は、住所地を所轄する法務局または大使館領事部に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有する書面を添付して「国籍離脱届」をして下さい(タイ国籍との重国籍者でタイ国籍を選択する人はこの方法によることになります)。
(ロ)外国の国籍を選択する方法。
当該外国の法令の定める方法により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、大使館領事部または市区町村役場に「国籍喪失届」をして下さい。
3. 国籍の選択をすべき期限
- 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
- 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。
※期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。
※昭和60年1月1日より前から重国籍となっている方については、期限内に国籍の選択をしなかったときでも、その期限が到来した時に日本国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
3.日本国籍の喪失
日本の国籍を喪失するのは、次の6つの場合があります。
1. 日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合(国籍法第11条第1項)
具体的な例としては、日本人女性がタイ人男性と婚姻した場合に、1960年2月1日付のタイ国改正国籍法の施行の前は、この日本人女性は、当時のタイ国国籍法によって、自己の志望によることなくタイ国籍を取得しましたが、同改正国籍法の施行により、「タイ国国民と婚姻する外国人女性は、省令の定める規則及び手続きに従って申請し、大臣の許可を得ることによりタイ国籍を取得する」そして「右タイ国籍の取得は、官報に告示されることにより効力を生ずる」と改訂され、この条項は現在のタイ国国籍法に至るまで引き継がれています。
従って、日本人女性が改正国籍法の施行後にタイ国籍を取得したときは、自己の志望によりタイ国籍を取得したことになり、タイ国官報への掲載日をもって、この日本人女性の日本国籍は喪失しています。
これに該当する方で、まだ「国籍喪失届」を出していない方は必要書類を準備して大使館領事部に届け出て下さい(国籍喪失届が未提出なために、日本の戸籍に同人の記載があることをもって、日本の国籍を持っていると考えられている方があるようですが、これは誤りで、日本の国籍は失っています)。
2. 重国籍の人が、外国の法令によってその国の国籍を選択した場合(国籍法第11条第2項)
これは後で述べる我国の国籍選択制度と類似した制度のある外国の国籍を持っている重国籍の人が、その制度に従って外国の国籍を選択すると、日本国籍を喪失することになります。
3. 外国で生まれ、出生によって重国籍となった人が、生まれた日から一定の期間内に出生届とともに国籍を留保する届出をしなかった場合(国籍法第12条)
これは、出生による日本国籍の取得で述べたように、出生届については、戸籍法第49条に「出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない」と規定されており、この届出期間内に日本国籍を留保する旨の出生の届出をしなかった場合は、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失してしまいます。
4. 重国籍の人が、日本の国籍を離脱する場合(国籍法第13条)
国籍の離脱は、法務大臣に届け出ることによってしますが、この届出があった時に日本の国籍を失います。
5. 重国籍の人が、国籍選択の催告を受けてから1ヵ月以内に日本の国籍を選択しなかった場合(国籍法第15条)
6. 法務大臣が、重国籍の人に日本の国籍の喪失宣告した場合(国籍法第16条)
これは後の国籍選択制度で述べるように、重国籍の人が「日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言」をする国籍選択届を出した後に、外国でその国の国民でなければ就任できないような公務員になるなど、選択宣言をした趣旨に著しく反するような行為があれば、法務大臣はその人に対して、日本の国籍の喪失を宣告することができることになっています。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
Eメール: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館 
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515