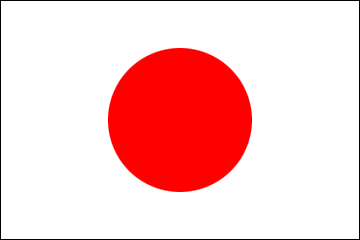領事関連情報
タイで「認知届」を行う場合
認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいい、裁判認知と任意認知とに大別されます。嫡出子でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に出生した子)に生来的に法律上の父を与えるところに認知の実質的な意味があります。
認知は、子を認知する父の本国法、又は認知される子の本国法いずれかの法律によって手続きをとることができます。ただし、日タイ両国間の渉外的認知の場合、子の本国法たるタイ国民商法が定める保護要件(認知に対する子と母双方の同意)を備えなければなりません。
すなわち、認知される子が未成年者などで、子本人に認知に同意する意思能力(承諾能力)がないと判断される場合は、父がタイ国裁判所に対して子(母)の同意に代わる後見的許可を求め、裁判所からその許可を相当とする司法命令を得ることで、保護要件を充足させなければなりません。これに対して、子に認知に同意できる一定の意思能力があると判断される場合は、子及び母が認知登録書に同意する旨の署名をすることで保護要件が充足されます。
このように、子の本国法たるタイ国民商法に基づき認知手続をとる場合は、同法に定める保護要件を充足させた上で、タイ国郡役場にて認知登録を成立させた後、日本側に認知届(報告的)を提出して下さい(下記B「報告的認知届」参照)。なお、タイ国での認知登録手続の詳細については、管轄のタイ国郡役場に直接ご照会下さい。
ところで、婚姻関係にない夫婦間に出生したタイ人子は、その後の父母の婚姻により、タイ国民商法上、父の法律上の子として扱われます。つまり、その子は嫡出子としての身分を自動的に取得し、認知が法律上できなくなることから、上述の保護要件が不要となります。
従って、この場合は、日本国民法に基づく認知届(創設的)を提出することができます(A.~創設的認知届~参照)。
なお、2009年1月の改正国籍法の施行に伴い、渉外、すなわち国際間の認知届(日本国民法に基づく創設的認知届)を受理するに当たり、民法779条の趣旨(父又は母が認知することができるのは嫡出でない子に限る)を徹底するため、新たに母の本国官憲(郡役場など)が発行した「独身証明書」等、認知した子が嫡出子でないことを確認することができる書面の提出が必要となりましたのでご注意下さい。
認知届の必要書類
下記の要領で在タイ日本国大使館領事部旅券・証明班戸籍国籍担当にご提出下さい。
※2024年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要となりますが、電子データ化されていない場合はご提出をお願いすることがあります(詳しくはこちら  )。
)。
A. 子の父母が婚姻している場合 (創設的認知届)
●日本人父
- 認知届 1通(当館にあり)
●タイ人母
- 子のタイ国出生登録証 : 原本
- 同和訳文 : 1通
出生登録証の和訳書式

出生登録証の和訳記入見本

- 子の住居登録証 : 原本
- 同和訳文 : 1通
住居登録証の和訳書式

- タイ人母の独身証明書 : 原本 (注)子の出生時に母が独身であったことを証明する書面
- 同和訳文 : 1通
B. 子の父母が婚姻していない場合 (報告的認知届)
●日本人父
- 認知届 1通(当館にあり)
●タイ人母
- 子のタイ国出生登録証 : 原本
- 同和訳文 : 1通
出生登録証の和訳書式

出生登録証の和訳記入見本

- 子の住居登録証 : 原本
- 同和訳文 : 1通
住居登録証の和訳書式

- タイ国郡役場発行の認知登録証 : 原本
- 同和訳文 : 1通
2. 届出人
認知する父親
3. 注意事項
- 創設的認知届は随時お受けできますが、報告的届出の場合は「認知登録証」が発行されてから3ヶ月以内となっております(判決に基づく裁判認知の場合は1ヶ月以内)。認知が成立すると出生時にさかのぼって効力が発生します。
- タイ国の場合、婚姻中に生まれた子、又は婚姻解消後310日以内に生まれた子は、夫又は前夫の子として推定されます。この推定が働く子の場合は、この推定を法的に排除しない限り(嫡出否認の訴えや親子関係不存在の確認など)、直ちに自己の子として認知することは当然できません。
- 2009(平成21)年1月1日、改正国籍法が施行され、出生後に日本人父又は母に認知されれば、一定の条件の下に、父母が婚姻していない場合においても届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました(同法3条)。
- 本邦市区町村役場に認知届を提出される方は、手続の詳細や必要書類につき、当該役場の担当者に直接ご照会下さい。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
Eメール: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館 
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515