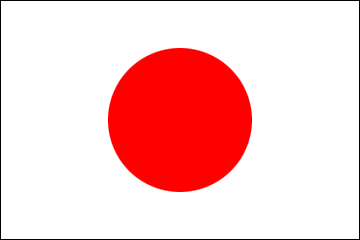領事関連情報
タイ国での離婚手続について
1. 日本人同士の離婚届について
日本人同士がタイ国において日本の民法の規定に基づき協議離婚する場合は、当館または日本の本籍地役場に直接または郵送等により離婚の届出をすることができます。
【届出必要書類】
- 離婚届 2通 → 離婚届の記入見本

※2024年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要となりますが、電子データ化されていない場合はご提出をお願いすることがあります(詳しくはこちら  )。
)。
【離婚届記載時の注意事項】
- 届書は、当館備え付けのもの、あるいは日本の役場からご入手されたものいずれでもご使用できます。
- 離婚届の住所欄は、居住しているタイ国の住所を日本語式の表記(たとえば、タイ国バンコク都パトムワン区ルンピニ町プルンチット路ランスワン小路●●/△番)で記入して頂く必要があります。記入の仕方が分からない場合は、空欄のままお持ち下さい。
- 証人(成人のご親族・知人等)2名の署名が必要となります(届書右欄)。
届出時、証人の方のご出頭は任意です。
証人がタイ在住者の場合の住所欄の記載については、上記2の場合と同様です。 - 離婚の場合、婚姻の際に戸籍の筆頭者にならなかった方(通常は妻となった人)は、離婚後の本籍地を新たに編製する必要があります。
従前の本籍地(婚姻前の親の本籍地など)とは異なる別の場所に本籍を定める場合は、実際に編成可能な表記(例えば●●県△△市◇◇区××2丁目3番地などのように正確な地番の表記が必要となります)をご確認の上お届け下さい。 - 婚姻の際に氏を変えた方(通常は妻となった人)は、当然に複氏(旧姓に戻る)しますが、それを望まない場合は、離婚の日から3カ月以内は届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を継続することができます。本届を希望される場合は届出時に担当者にお申しつけ下さい。
- 未成年者の子がいる場合、父母の協議によりそのいずれか一方を親権者として定める必要があります(届書の(5)欄)。
【その他の注意事項】
- 当館に届出をされた場合、当館が本届を実際に受理した日(通常は届出日)が離婚の成立日となります。
- 届書は、外務省経由で各本籍地役場に送付される関係上、新戸籍が編成されるまで、最低で1ヶ月ほど時間を要します。
- 離婚によりその氏を変更した方(通常は妻)は、速やかに旅券の申請手続(現旅券の訂正又は新規旅券の発給申請)を始め、運転免許証の訂正、銀行、カード会社等に対する所要の届出を行う必要があります。
- その際、離婚後の新たな戸籍謄(抄)本のご提出が必要となりますので、本手続をできるだけ早期にされたい方は、日本の本籍地役場に直接、お届けいただくことをお勧めいたします。
日本の役場に届出される場合は、その方法や必要書類につき、事前に詳しく役場の担当者にお問い合わせください。
2. 日本人とタイ人の離婚届について
タイ国に居住している日本人とタイ人夫婦とが離婚する場合の渉外的離婚手続については、法の適用に関する通則法(わが国の国際私法)、日本国民法及びタイ国民商法等の諸法令が重複適用されます。
主な手続の種類を大別すると次のとおりとなります。
【国際私法について】
国際結婚・貿易取引等のような複数の国に関わる渉外的私法関係を処理するにあたり、いずれの国の法を適用するかを指定する法。抵触法ともいう。外国判決の承認・執行や裁判管轄権の問題も扱う。
1. 日本国民法に基づく離婚手続き(窓口:日本の本籍地役場)
夫婦の一方である日本人配偶者の常居所(下記参照)が日本にあると認められるときは、日本国民法(以下、単に「民法」という)に基づく離婚届を日本の本籍地役場(市区町村)に対して届出(郵送また第三者による持参提出)をすることができます(法の適用に関する通則法27条但書、戸籍法40条、民法764・741・739条)。
【常居所について】
常居所とは、単なる居所とは異なり、人が相当長期間にわたって居住する場所を意味し、住所に類似した概念とされています。住民登録があれば、通常、日本に常居所があると推定されますが、その認定は行政講学上、居住年数、居住目的、住居等の諸要素を総合的に勘案してする必要があるとされています。よって、その具体的認定は日本の市区町村役場がおこないます。
必要書類
- 離婚届 2通
- タイ人配偶者の国籍を証明する書類(タイ国住居登録証や旅券等)
- 上記和訳文(要翻訳者名明記)
翻訳箇所 : 1頁、 個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)
*タイ人配偶者側の必要書類については、役場により取り扱い(原本性や翻訳の様式等)の相違がありますので、お届けになる役場に直接ご確認下さい。
留意事項
- 日本人配偶者の常居所が日本になければなりません。 届出に際し、当事者夫婦に出頭義務はありません。ただし、本届出は、外国人配偶者も届出人となる創設的届出となりますので、届出の窓口は日本の本籍地役場のみとなります。大使館または総領事館には届出をすることができません(戸籍法40条)のでご注意ください。
- 当初の婚姻の準拠法が民法以外の他国の法律(タイ国法など)であっても、協議により届出をすることができます(民法739条・764条)。
- 証人(成年に達している者)2名の連署が必要です(民法739条2項)。届出に際し、証人の方に出頭義務はありません。
- 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者と定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。
- 婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更することができます(戸籍法107条3項)。
- この離婚届が受理されると、日本人配偶者の戸籍に離婚の事実が記載されます。タイ人配偶者の方は、タイ国郡役場での自らの離婚手続(家族状態登録簿の変更)のため、本戸籍の翻訳が必要となります。当館では、申請に基づき、本手続に必要な証明書(離婚証明書)を発行しています。
離婚証明書の発行のための必要書類は「戸籍記載事項証明」をご参照ください。
2. タイ国民商法に基づく離婚手続(窓口:タイ国郡役場)
双方が離婚について協議が整えば、タイ国法に基づく協議離婚の登録をすることができます(タイ国民商法1515・1531条)。
タイでの離婚登録手続の詳細については、タイ国郡役場にお問い合わせください。
*タイ国での離婚手続終了後、引き続いて日本国側での離婚手続をおこなう(窓口:大使館・総領事館又は日本の本籍地役場)
タイ国での離婚登録後、3ヶ月以内に、大使館・総領事館または日本の本籍地役場に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法41条、民法764・741条)。この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。
日本国側に離婚届(報告的)を提出するために必要な書類
- 離婚届 2通
- タイ国離婚登録証(原本に限る)*親権者として監護すべき子どもがいる場合は、タイ国離婚登録簿(バイタビアンガーンヤー)もあわせてご提出ください。
- 上記和訳文(要 翻訳者明記)
離婚登録証の和訳書式

離婚登録簿の和訳書式

- タイ国住居登録証(原本に限る)
- 上記和訳文(要 翻訳者明記)翻訳箇所 : 1頁、 個人頁(配偶者)18頁(該当ある場合のみ)
住居登録証の和訳書式

留意事項
- 報告的届出なので、日本の常居所の有無にかかわらず、大使館・総領事館または日本の本籍地役場のいずれにも届出することができます。ただし、日本の本籍地役場に届け出る場合、必要書類については、役場の担当者に詳しくお問い合わせください(役場によっては、上記以外の書類が必要となる可能性もあります)。
- 離婚する夫婦に未成年者の子がある場合は必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません(戸籍法76・78条、民法819条・766条)。タイ国役場が発行する離婚登録簿にもその旨の記載がなければなりません。
- 報告的届出のため、証人は不要です。
- タイ国での離婚登録日から3ヶ月以内に届出が必要です(戸籍法41条)。なお、報告的届出のため、本来、届出人は日本人配偶者の方のみとなります(戸籍法40条)が、未成年の子がいる場合は、届出人欄に旧親権者として外国人配偶者の署名も必要となりますのでご注意ください。
3. タイ国での確定裁判に基づく離婚手続(窓口:タイ国裁判所)
タイ国に居住する日本人とタイ人夫婦が、離婚について協議が整わない場合、裁判を申し立てることができます。そして、タイ国裁判所における離婚判決が確定した場合、その離婚判決は、民事訴訟法118条に規定する要件(後記参照)を具備する限り、日本においても効力を有します。この場合、判決のあった日から10日以内に、日本の市区町村役場または大使館・総領事館に離婚届(報告的)を提出しなければなりません(戸籍法77・63条、民法764・741条)。
この届出をしてはじめて両国での離婚手続が完了します。
【民事訴訟法118条に規定する4要件】
- 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
- 敗訴の被告が公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼び出し等の送達を受けたこと又は被告が応訴したこと
- 判決の内容及び訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと
- 相互の保証があること
必要書類
- 離婚届 2通
- タイ国裁判所判決謄本(原本に限る)
- 上記和訳文(要 翻訳者明記)
- タイ国裁判所判決確定証明書(原本に限る)
- 上記和訳文(要 翻訳者明記)
留意事項
- 報告的届出のため、証人は不要です。
- タイ国での裁判確定から10日以内に届出が必要です (戸籍法77・63条)。なお、報告的届出のため、届出人は日本人配偶者の方となります。タイ人配偶者の出頭及び署名は任意です。
3. その他(配偶者と死別した場合)
1. 日本人ご夫婦の場合
配偶者の方が死亡した場合、婚姻関係は当然に終了しますので、離婚届のご提出は必要ありません。
ただし、氏に関しては離婚(離別)の場合と違って、婚姻前の氏に当然に戻るわけではありません(民法751条1項)。婚姻の際に氏を変更した生存配偶者は「復氏届」(戸籍法95条)を届け出て、はじめて、婚姻前の氏に戻ることができます(死亡した配偶者の親族の同意・家庭裁判所の許可等は不要です)。
また、姻族関係は、離婚による場合、婚姻関係の終了と同時に終了します(民法728条1項)。これに対して、夫婦の一方が死亡しても、その配偶者の親族と生存配偶者との姻族関係は当然には終了しません。生存配偶者の自由意思によってその旨届出をすることにより、これを終了させることができます(姻族関係終了届:民法728条2項、戸籍法96条)。
この姻族関係の終了の意思表示によって、離婚した配偶者やその血族との親族関係は終了し、扶養や相続に関する権利義務といった問題は今後生じなくなります。
2.日本人とタイ人のご夫婦で、タイ人配偶者の方が死亡された場合
配偶者の方が死亡した場合、婚姻関係は当然に終了しますので、離婚届のご提出は必要ありません。
ただし、配偶者が外国人の場合、その方と死別して、婚姻関係が終了しても、婚姻前の氏に当然に戻るわけではありません。婚姻に際し、タイ人配偶者の氏に姓を改めた方は、離婚の日から3ヶ月以内に限り、届出により、元の日本人としての姓に変更(複氏)することができます(戸籍法107条3項)。
また、タイ人配偶者の方の死亡の事実については、日本人配偶者が申し出ることによって、その方(日本人)の戸籍にその旨(死亡者の氏名・死亡日時や場所・届出者氏名等)の記載を要することになっています。その申出に必要な書類は次のとおりです。
必要書類
- 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(当館にあり)
- タイ人配偶者のタイ国死亡登録証(モラナバット)(原本に限る)
- 上記和訳文(要 翻訳者明記)
参考情報
ハーグ条約に関するリーフレット「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
Eメール: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館 
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515